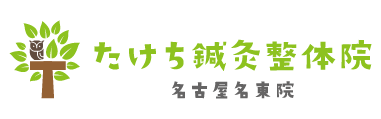
 院長:武智
院長:武智お気軽にご相談ください!
こんにちは、たけち鍼灸整体院・名古屋名東院のたけちです。突然ですが、繰り返すめまいや耳鳴りに悩まされて「もう一生付き合っていくしかないのかな」なんて諦めかけていませんか。病院ではメチコバールなどのお薬を処方されて、一時的には楽になるけれど、根本的な解決には至らず悩んでいる方も多いのではないでしょうか。.
実はメニエール病の症状改善には、薬物療法と並行して日々の食事や栄養管理がとても重要な役割を果たします。今回は栄養という視点から、どのように体質を整えていけば良いのか、私の臨床経験も交えながらお話ししていきますね。


当院にいらっしゃる患者さんも「薬を飲んでいるけど良くならない」という方が本当に多いです。でも栄養バランスを見直すだけで驚くほど症状が軽くなるケースをたくさん見てきました。一緒に改善の道を探していきましょう
病院でメニエール病の治療を受けると、ビタミンB12製剤であるメチコバールが処方されることが多いです。これは末梢神経に働きかけて神経細胞を修復する役割があり、めまいや耳鳴り、難聴といった症状の緩和に用いられています。
確かに医薬品としてのビタミンB12は効果的ですが、薬だけに頼っていては根本的な体質改善にはなかなか結びつきません。なぜなら、メニエール病の背景には栄養の偏りや不足、生活習慣の乱れ、ストレスなど複合的な要因が絡み合っているからです。
実際に当院でカウンセリングを行うと、食生活が乱れている方や特定の栄養素が不足している方が非常に多いと感じます。忙しい毎日の中でコンビニ食や外食が続いたり、野菜や魚をあまり食べていなかったり。そういった積み重ねが、知らず知らずのうちに体の回復力を奪ってしまうんです。
だからこそ、薬による対症療法と並行して、食事から必要な栄養素をしっかり摂ることが症状改善の大きな鍵になります。
メチコバールとして処方されるビタミンB12ですが、実は日々の食事からも十分に摂取できる栄養素です。しじみ、あさり、牡蠣などの貝類や、サンマ、イワシといった青魚に豊富に含まれています。
動物性たんぱく質に多く含まれるため、野菜中心の食生活では不足しがちになりますので注意が必要です。毎日の食卓に意識的に取り入れることで、薬だけに頼らない体づくりができるようになります。
ビタミンB12以外にも、メニエール病の症状を和らげるために積極的に摂りたい栄養素がいくつかあります。体内の水分バランスを整えたり、神経機能をサポートしたり、血流を改善したりする働きを持つ栄養素を日常的に取り入れることで、発作の頻度が減ったり症状が軽くなったりする方が本当に多いんです。
カリウムは体内の余分な塩分(ナトリウム)を排出し、水分バランスを調整する働きがあります。メニエール病は内耳にリンパ液が溜まることで起こるため、カリウムの摂取は症状緩和に役立つとされています。
ほうれん草、きゅうり、アボカド、バナナ、メロン、海藻類などに多く含まれていますので、毎日の食事に取り入れてみてください。
マグネシウムは神経機能の安定や血管の拡張に関与し、血流改善に役立ちます。ひじきやわかめなどの海藻類、アーモンドやカシューナッツなどのナッツ類、豆腐や納豆といった豆類に豊富です。
少量ずつでも毎日続けて摂取することが大切です。
ビタミンB1、B6、B12といったビタミンB群は、神経機能の維持やエネルギー代謝に不可欠です。豚肉、うなぎ、かつお、卵、乳製品、玄米、豆類などバランス良く様々な食材から摂取しましょう。特にビタミンB1は中枢神経や末梢神経の働きを助け、めまいの改善に効果的とされています。
ビタミンCは抗酸化作用があり、ストレスに対する体の抵抗力を高めます。柑橘類、イチゴ、ブロッコリー、パプリカなどに豊富で、加熱に弱いため生で食べられるものは積極的に取り入れましょう。またビタミンEは血流改善に役立ち、油脂類、種実類、魚類、野菜などに含まれています。
耳に酸素や栄養が行き渡ることで内耳の働きが良くなり、症状が緩和されると考えられています。
意外と見落とされがちですが、潜在性鉄欠乏症がめまいの原因になっているケースも少なくありません。当院でも血液検査で貯蔵鉄(フェリチン)が低下している方が多く見られ、鉄分補給により症状が改善した例を数多く経験しています。レバー、赤身肉、ほうれん草、小松菜などを意識的に摂りましょう。
栄養素を摂ることと同じくらい大切なのが、塩分と水分のコントロールです。ナトリウム(塩分)の過剰摂取は体内の水分バランスに影響し、内リンパ水腫を悪化させる可能性があります。だからこそ減塩を心がけることが重要なのですが、同時にこまめな水分補給も欠かせません。脱水は血流を悪化させ、内耳機能にも悪影響を及ぼします。
適切な水分補給により、抗利尿ホルモンの分泌を抑制でき、内耳に水が貯まりにくくなるとも言われています。水やノンカフェインのお茶(麦茶、ルイボスティーなど)を少量ずつ頻繁に飲むのが理想的です。一度に大量に飲むのではなく、こまめに補給することを意識してみてください。
食物繊維には血糖値、中性脂肪値、コレステロール値などを下げる働きがあります。野菜や豆類、穀物、海藻などに多く含まれており、これらを積極的に摂ることで血流が良くなります。
血流が改善されれば耳に酸素や栄養が行き渡って働きが良くなり、メニエール病の症状が緩和されると考えられています。毎朝の麦ごはんと納豆、卵、海苔の組み合わせや、昼食と夕食に野菜炒めにきくらげを加えるといった工夫も効果的です。
逆に症状を悪化させる可能性がある食べ物や習慣もあります。塩分の多い食事、アルコールの多飲、カフェインの過剰摂取は控えめに。また、加工食品やファストフード、スナック菓子などは栄養バランスが偏りがちです。夜遅い食事や不規則な食生活も自律神経を乱し、症状悪化につながります。
過度のストレスや疲労、睡眠不足も大敵です。急激な体位変換や激しい運動も避けた方が良いでしょう。日々の生活習慣全体を見直すことが、症状改善への近道なのです。
当院では鍼灸整体治療に加えて、提携医療機関である野口基礎医療クリニックで解析された血液検査の結果を活かし、栄養や免疫のセルフケアに関するサポートにも力を入れています。一人ひとりの栄養状態を詳しく分析し、何が不足しているのか、どんな食事を心がければ良いのかを具体的にアドバイスしています。
姿勢分析、関節可動域検査、東洋医学検査、栄養解析、過敏症チェックという5つの独自検査で現在の状態を可視化し、症状の原因を特定します。検査もせずいきなり施術をスタートする治療院も増えていますが、原因を特定できなければ何度も同じ症状を繰り返すことになってしまいます。
食事療法は体質改善や栄養バランスの調整により、体の根本からの健康促進や症状の土台を整える役割があります。一方、鍼灸治療は自律神経の調整や血行促進により、めまいや耳鳴りといった直接的な症状の緩和を図ります。この二つを組み合わせることで相乗効果が生まれ、改善スピードが格段に上がるのです。
栄養療法や食事の見直しは、一度きりのものではなく継続することが何より重要です。焦らず、自分自身の体と向き合いながら、長期的な視点で取り組むことがメニエール病の症状を和らげ、快適な日常生活を送るための鍵となります。最初は大変に感じるかもしれませんが、少しずつでも良いので日々の食事に意識を向けてみてください。
当院に通われている患者さんの中には、「薬を飲んでも良くならなかったのに、食事を変えたら発作が減った」「栄養指導を受けてから体調が安定した」という声をたくさんいただいています。体は正直で、良いものを取り入れれば必ず応えてくれます。
メニエール病の改善には、メチコバールなどの薬物療法も大切ですが、それだけでは不十分です。日々の食事から必要な栄養素をバランス良く摂り、生活習慣を整え、自律神経にもアプローチすることで、薬だけに頼らない体づくりが可能になります。ビタミンB12をはじめ、カリウム、マグネシウム、ビタミンC、E、鉄分、食物繊維など、体が必要としている栄養素を意識的に取り入れましょう。
もし「何から始めれば良いか分からない」「自分に合った栄養バランスが知りたい」と感じたら、ぜひ専門家に相談してください。当院では詳細な検査と栄養解析により、あなたに最適な食事プランと施術プランをご提案します。つらい症状を一人で抱え込まず、いつでもお気軽にご相談くださいね。一緒に、自分らしい元気な毎日を取り戻しましょう。

