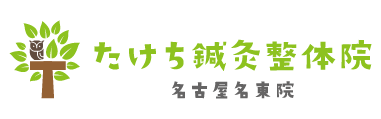
 院長:武智
院長:武智お気軽にご相談ください!
たけち鍼灸整体院・名古屋名東院、院長のたけちです。本日は今日は、梅雨の季節になると多くの方からご相談いただく「気圧頭痛」についてお話しします。


気圧頭痛について私が詳しくお話しします


雨の日や天気が崩れる前になると、頭が重くなったり、ズキズキとした痛みを感じたりすることはありませんか?
特に30代から50代の女性の方には、この時期特有の体調不良として頭痛を訴える方が多くいらっしゃいます。今回は、気圧頭痛がなぜ起こるのか、その正体と日常生活でできる対策について、わかりやすくお伝えしていきます。
梅雨の時期になると、毎日のように雨が降り、空気が重たく感じることが多くなります。この時期に頭痛が増えるのは、決して気のせいではありません。
実際に、梅雨入りしてから「頭が重い」「天気が悪いと頭痛がひどくなる」と感じる方が増えます。これは、気圧の変化が体に影響を与えているためです。
気圧が下がると、私たちの体は外から受ける圧力が弱くなります。その結果、血管が広がりやすくなり、脳の血管も膨張します。この膨張が神経に触れることで、ズキズキとした痛みが現れます。
特に片頭痛を持っている方は、気圧の変化に敏感で、痛みが強く出やすい傾向があります。
また、気圧の変化は自律神経のバランスにも影響します。自律神経は、体温調整や血流、消化などをコントロールしている大切な神経です。気圧が急に下がると、この自律神経が乱れやすくなり、血管の拡張や神経の過敏さを引き起こしてしまいます。これが、梅雨の時期に頭痛が多発する大きな理由です。
梅雨といえば、湿度の高さも特徴的です。湿度が高いと、体の中の水分バランスが崩れやすくなります。汗や尿として水分がうまく排出されず、体内に余分な水分がたまりやすくなります。その結果、むくみや頭の重さを感じやすくなり、頭痛の原因となることもあります。
特に、もともと水分代謝がうまくいかない体質の方や、普段からむくみやすい方は、梅雨の時期に頭痛が出やすい傾向があります。体の中の水分バランスが崩れると、血液の流れも悪くなり、頭痛だけでなく倦怠感やだるさ、眠気などの症状も現れやすくなります。
このように、気圧や湿度など天気の変化によって起こる体調不良は「気象病」とも呼ばれています。気象病には頭痛のほか、めまいや耳鳴り、関節の痛み、古傷の痛みなどさまざまな症状がありますが、中でも頭痛は最も多い症状です。
気象病の原因は、自律神経の乱れや体内の水分バランスの崩れ、血管の拡張などが複雑に絡み合っています。
とくに、女性はホルモンバランスの変化も加わるため、気象病になりやすい傾向があります。月経周期や更年期など、女性ホルモンの変動が大きい時期は、自律神経も影響を受けやすく、気圧頭痛を感じやすくなるのです。
梅雨の時期に多い頭痛には、主に「片頭痛」と「緊張型頭痛」の2種類があります。片頭痛は、こめかみから額にかけてズキズキと脈打つような痛みが特徴です。気圧が下がることで血管が広がり、神経を刺激することで痛みが発生します。
一方、緊張型頭痛は、頭全体がぎゅーっと締め付けられるような重い痛みです。これは、気圧の変化によって自律神経が乱れ、筋肉が緊張しやすくなるために起こります。特に首や肩のこりが強い方は、緊張型頭痛が出やすい傾向があります。
気圧頭痛を根本から治すことは難しいですが、日常生活の中で症状を和らげたり、予防したりすることは十分に可能です。まず大切なのは、自律神経を整えることです。
規則正しい生活リズムを心がけ、睡眠をしっかりとることが基本です。朝は決まった時間に起きて、太陽の光を浴びることで体内時計をリセットしましょう。
また、適度な運動も効果的です。ウォーキングやストレッチなど、軽く汗をかく程度の運動を習慣にすると、血流が良くなり、体内の水分バランスも整いやすくなります。運動はストレス解消にもつながり、自律神経の安定にも役立ちます。
耳のマッサージもおすすめです。耳たぶを軽くつまんで横に引っ張ったり、やさしく回したりすることで、内耳の血流が良くなり、気圧の変化を感じにくくなります。これは、朝昼晩の3回、定期的に続けると予防効果が高まります。
食事面では、塩分や水分の摂りすぎに注意しましょう。体内に余分な水分をため込まないよう、バランスの良い食事を心がけてください。特に、カリウムを多く含む野菜や果物は、余分な水分の排出を助けてくれます。
頭痛がひどいときは、無理をせず休息をとることも大切です。片頭痛の場合は、部屋を暗くして静かな場所で横になると痛みが和らぎやすくなります。冷たいタオルでこめかみを冷やすのも効果的です。
また、コーヒーや紅茶などに含まれるカフェインには血管を収縮させる働きがあるため、痛みが出そうなときに適量を摂るのもひとつの方法です。ただし、カフェインの摂りすぎには注意しましょう。
市販の鎮痛薬や漢方薬(五苓散など)も、気圧頭痛の改善に役立つことがあります。薬を使う場合は、用法や用量を守り、必要に応じて医師や薬剤師に相談してください。
梅雨時期は、普段よりも体調の変化に敏感になり、自分の体をいたわることが大切です。
梅雨の時期は、どうしても気圧や湿度の影響で体調を崩しやすくなります。気圧頭痛は、体が環境の変化にうまく対応できないときに現れるサインです。自分の体のリズムを大切にし、無理をせず、できる範囲でセルフケアを続けていきましょう。
「今日は頭が重いな」「天気が悪くなりそうだな」と感じたときは、早めに対策をとることが大切です。自分の体の声に耳を傾けて、無理をしないことが、梅雨の時期を快適に過ごすポイントです。
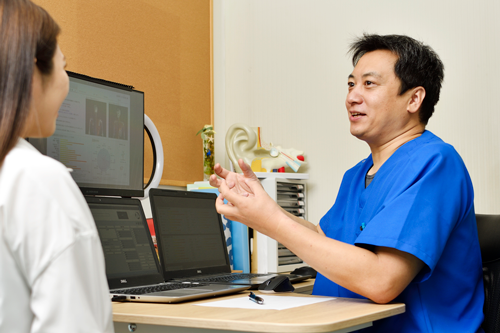
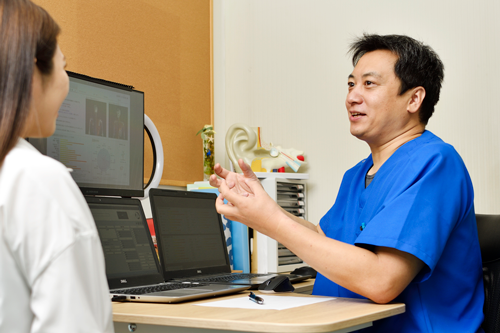
梅雨の季節に多発する気圧頭痛は、気圧や湿度の変化による自律神経の乱れや血管の拡張、体内の水分バランスの崩れが主な原因です。女性はホルモンバランスの影響も受けやすいため、特に注意が必要です。
自分の体と向き合い、無理せず過ごすことが、健康への第一歩です。