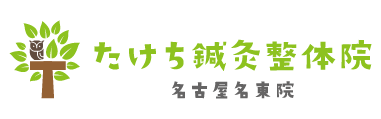
 院長:武智
院長:武智お気軽にご相談ください!
こんにちは、たけち鍼灸整体院・名古屋名東院のたけちです。今日は多くの方からご相談をいただく「耳閉感の耳がふさがってめまいが起こる」症状についてお話しします。
この症状は決して珍しいものではありません。しかし、どのような仕組みで起こるのか、どう対処すればよいのかを知らない方が多いのが現状です。
この記事では、私の臨床経験をもとに、耳閉感とめまいの関係性や原因、そして適切な対処法について詳しく解説していきます。


耳の詰まり感とめまいでお困りの方に、わかりやすくお伝えします


耳閉感とめまいが同時に現れる症状は、多くの場合、耳の奥にある内耳という部分の働きに関係しています。内耳は聴覚だけでなく、体のバランスを保つ重要な役割も担っているのです。
耳の詰まり感とめまいが同時に起こる理由を理解するためには、まず耳の構造を知ることが大切です。耳は外耳、中耳、内耳の3つの部分に分かれており、それぞれが異なる働きをしています。
外耳は音を集める部分で、中耳は音を増幅させる働きがあります。そして内耳には、音を感じ取る蝸牛という器官と、体のバランスを保つ前庭器官があります。この前庭器官が正常に働かないと、めまいが起こるのです。
耳閉感は、主に中耳や内耳の圧力バランスが崩れることで生じます。風邪をひいたときや気圧の変化、ストレスなどが原因となることが多いです。この圧力バランスの乱れが内耳の前庭器官にも影響を与えると、めまいが発生するのです。
耳閉感とめまいが同時に現れる症状には、いくつかの代表的な病気が関係しています。最も多く見られるのがメニエール病です。この病気は内耳のリンパ液が増えすぎることで起こり、耳の詰まり感、めまい、耳鳴り、難聴などの症状が現れます。
突発性難聴も注意が必要な病気の一つです。急に聞こえにくくなると同時に、耳閉感やめまいを感じることがあります。この場合は早期の治療が重要になります。
また、中耳炎や外耳炎などの炎症が原因となることもあります。特に慢性的な中耳炎では、耳の詰まり感が長期間続き、時折めまいを感じることがあります。耳管狭窄症という病気では、鼻と耳をつなぐ管が狭くなることで、耳の圧力調整がうまくいかず、詰まり感とめまいが生じます。
病気以外にも、日常生活の中で耳閉感とめまいを引き起こす要因があります。最も身近なものが気圧の変化です。台風や低気圧が近づくとき、飛行機に乗ったとき、エレベーターで高層階に上がるときなどに症状を感じる方は多いでしょう。
ストレスも大きな要因の一つです。精神的な緊張や疲労が続くと、自律神経のバランスが乱れ、内耳の血流が悪くなります。その結果、耳閉感やめまいが起こりやすくなるのです。
睡眠不足や不規則な生活リズムも症状を悪化させます。体の回復機能が低下し、内耳の働きにも影響を与えるためです。また、水分不足や塩分の摂りすぎも、体内の水分バランスを崩し、内耳に負担をかけることがあります。
耳閉感とめまいの症状は、原因によって現れ方が異なります。メニエール病の場合、回転性のめまいが特徴的で、グルグルと回る感じが数時間続くことがあります。同時に耳の詰まり感、耳鳴り、聞こえにくさも感じられます。
突発性難聴では、急に片方の耳が聞こえなくなり、同時に耳閉感とめまいが現れます。症状は急激に始まることが多く、朝起きたときに気づくケースが多いです。
良性発作性頭位めまい症では、頭の位置を変えたときに短時間のめまいが起こります。耳閉感はそれほど強くありませんが、頭を動かすたびにめまいを感じるのが特徴です。中耳炎が原因の場合は、耳の痛みや発熱を伴うことがあります。
耳閉感とめまいの症状が現れたとき、どのタイミングで病院を受診すべきか迷う方も多いでしょう。急激に症状が現れた場合、特に突然聞こえにくくなった場合は、できるだけ早く耳鼻咽喉科を受診することが大切です。
また、激しいめまいで立っていられない、吐き気や嘔吐がひどい、高熱がある場合も緊急性が高いです。症状が軽くても、数日間続く場合は専門医の診察を受けることをお勧めします。
受診する科は、まず耳鼻咽喉科が適切です。耳や鼻、のどの専門医が詳しく診察し、必要に応じて聴力検査や画像検査を行います。めまいの症状が強い場合は、めまい外来のある病院を選ぶのも良いでしょう。


症状が軽い場合や、病院受診前の応急処置として、自宅でできる対処法があります。まず大切なのは安静にすることです。めまいがあるときは無理に動かず、横になって休むことが基本です。
耳閉感を和らげるために、あくびをしたり、つばを飲み込んだりして耳抜きを試してみましょう。ただし、強く鼻をかんだり、無理に耳抜きをしたりするのは避けてください。症状を悪化させる可能性があります。
水分補給も重要です。脱水状態は症状を悪化させるため、こまめに水分を摂取しましょう。ただし、カフェインやアルコールは避け、水や薄いお茶を選ぶようにしてください。十分な睡眠とストレス管理も症状改善に役立ちます。
耳閉感とめまいの予防には、日常生活での注意が大切です。規則正しい生活リズムを心がけ、十分な睡眠時間を確保しましょう。ストレスをため込まないよう、適度な運動や趣味の時間を作ることも重要です。
食事では、塩分を控えめにし、バランスの良い食事を心がけましょう。特にメニエール病の場合、塩分の摂りすぎは症状を悪化させる可能性があります。水分補給も忘れずに行い、体の水分バランスを保つことが大切です。
風邪やアレルギーの管理も予防につながります。鼻づまりが続くと耳管の働きが悪くなり、耳閉感を引き起こしやすくなります。花粉症などのアレルギー症状がある場合は、適切な治療を受けることも大切です。
医療機関での治療と並行して、鍼灸治療などの補完的なアプローチも症状改善に役立つことがあります。
鍼灸治療では、耳周辺のツボや全身のバランスを整えるツボに刺激を与えることで、血流を改善し、自律神経のバランスを整えます。ストレスが原因の場合は、特に効果的なアプローチとなることがあります。
ただし、急性期の症状や原因が明確でない場合は、まず医療機関での診察を受けることが最優先です。補完的な治療は、医師の診断と治療方針を理解した上で検討することが大切です。
耳閉感とめまいが同時に現れる症状は、内耳の働きに関係していることが多く、様々な原因が考えられます。症状が急激に現れた場合や長期間続く場合は、早めに専門医の診察を受けることが重要です。
日常生活では、規則正しい生活リズム、適切な水分補給、ストレス管理などを心がけることで、症状の予防や改善につながります。一人で悩まず、適切な医療機関での治療を受けながら、必要に応じて補完的なアプローチも検討してみてください。
症状でお困りの際は、まず耳鼻咽喉科を受診し、正確な診断を受けることから始めましょう。早期の適切な対処が、症状改善への第一歩となります。