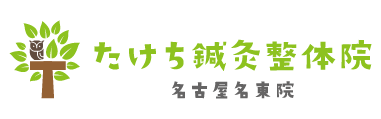
 院長:武智
院長:武智お気軽にご相談ください!
たけち鍼灸整体院・名古屋名東院、院長のたけちです。本日は梅雨時期に多くの方が気になる「気圧・天気とメニエール病の関係」についてお話しします。


気圧・天気とメニエール病の関係について私が詳しくお話しします


じめじめとした空気や、天気の急な変化で体調がすぐれないと感じる方も多いのではないでしょうか。特に、めまいや耳鳴り、難聴といった症状でお悩みの方には、この季節ならではの注意点がいくつかあります。
梅雨に入ると、湿度が高くなり、気圧も不安定な日が続きます。このような環境の変化は、メニエール病の症状を悪化させる一因となります。メニエール病は内耳の異常によって引き起こされる病気で、めまいや耳鳴り、難聴などが主な症状です。
特に6月から7月の梅雨時期は、気圧の急な変化や高い湿度が重なり、症状が長引いたり、強く出たりすることが多いと感じています。
気圧が下がると、体の中でも特に内耳が影響を受けやすくなります。内耳にはリンパ液が流れていて、このバランスが崩れると、めまいや耳鳴りが起こりやすくなります。
急激な気圧の変化は、内耳のリンパ液の圧力を調整する働きを乱すため、発作のきっかけになることがあります。特に台風や前線が近づく時期は、症状が悪化しやすいので注意が必要です
梅雨の時期は湿度が高くなり、体の水分バランスも崩れやすくなります。湿度が高いと、体の中に水分がたまりやすくなり、内耳にもリンパ液が溜まりやすくなります。このリンパ液の増加が、内耳の圧力を高めてしまい、症状の悪化につながることがあります。
体がむくみやすい方や、普段から水分代謝がうまくいっていないと感じる方は、特に注意が必要です。
天候の変化は、体だけでなく心にも影響を与えます。気圧や湿度の変化が続くと、知らず知らずのうちにストレスがたまりやすくなります。このストレスが、さらにメニエール病の症状を悪化させる悪循環を生み出すことがあります。
天気が不安定な日は、気持ちも不安定になりがちです。自分の体調や気分の変化に気づいたら、無理をせず、ゆっくり休むことも大切です。
メニエール病と自律神経のバランスも深く関係しています。気圧の変化は自律神経に影響を与え、交感神経と副交感神経のバランスが崩れることで、めまいや耳鳴りが起こりやすくなります。
特に、もともと自律神経のバランスが乱れやすい方や、ストレスや疲れがたまりやすい方は、天気の変化で症状が強く出ることがあります。生活リズムを整えたり、深呼吸などでリラックスする時間を作ることが、自律神経の安定に役立ちます。
メニエール病は女性に多い傾向があり、特に30代から50代の方に多く見られます。不規則な生活や、仕事や家事、育児、介護などで忙しい方は、天気の影響を受けやすいと感じることがあるかもしれません。
梅雨時期は、普段よりも体調の変化に敏感になり、自分の体をいたわることが大切です。
梅雨の時期は、規則正しい生活を心がけることが大切です。睡眠をしっかりとり、バランスの良い食事を意識しましょう。体を冷やさないようにしたり、適度な運動を取り入れることで、体の水分代謝や自律神経のバランスを整えることができます。
また、ストレスをためないように、趣味の時間を持ったり、深呼吸や軽いストレッチをするのもおすすめです。カフェインの摂取や過度の飲酒は血流を悪くし、むくみの原因となってしまうので、控えめにしたほうが良いでしょう
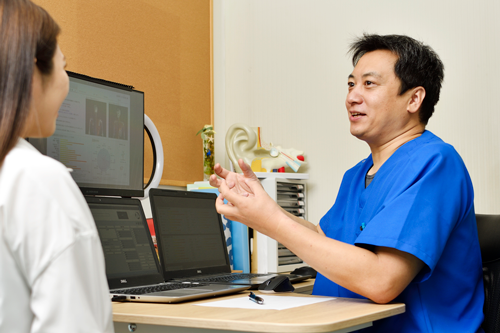
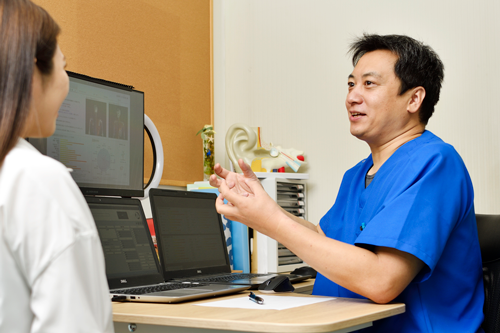
梅雨の時期は、気圧や湿度の変化がメニエール病の症状に大きく影響します1。体調や気分の変化に敏感になりやすい季節ですが、生活リズムを整えたり、ストレスをためない工夫をすることで、症状の悪化を防ぐことができます。
自分の体と向き合い、無理せず過ごすことが、健康への第一歩です。