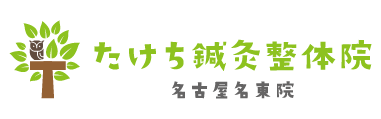
 院長:武智
院長:武智お気軽にご相談ください!
こんにちは、たけち鍼灸整体院・名古屋名東院のたけちです。本日は姿勢と自律神経の深いつながりについてお話しします。最近、肩こりや頭痛、疲れやすさ、なんとなく気分が落ち込むといった不調を感じている方が増えています。


姿勢と自律神経についてわかりやすく説明します
実は、こうした体や心の不調の背景には、姿勢と自律神経の関係が大きく関わっていることをご存知でしょうか。今回は、日常生活の中で見落とされがちな姿勢と自律神経のつながりについて、私の経験も交えながらわかりやすく解説していきます。
自律神経は、私たちが意識しなくても体の働きを調整してくれる神経です。呼吸や心臓の動き、消化や体温調節など、生命維持に欠かせない機能を自動的にコントロールしています。この自律神経には交感神経と副交感神経の2つがあり、互いにバランスを取りながら体調を整えています。
一方、姿勢は筋肉・骨格・神経の働きがうまく協調することで保たれています。現代では、長時間のデスクワークやスマートフォン操作により、前かがみや猫背などの悪い姿勢が習慣化しやすくなっています。実はこの姿勢の乱れこそ、自律神経に大きな影響を与える要因のひとつなのです。


悪い姿勢が続くと、首や肩、背中の筋肉に負担がかかり、血流が悪化します。血流の悪化は脳や体全体への酸素供給を妨げ、結果的に交感神経が優位な状態が長く続いてしまいます。その状態では体が常に緊張し、リラックスしにくくなってしまうのです。
また、前かがみの姿勢では胸が圧迫され、浅い呼吸になりがちです。浅い呼吸は副交感神経の働きを弱め、身体の回復・休息機能を妨げます。このように、姿勢の崩れは単なる見た目の問題にとどまらず、自律神経のバランスにも深く影響しています。
姿勢を整えることで、自律神経は安定しやすくなります。胸を開くように姿勢を意識するだけで、呼吸は自然と深くなり、副交感神経が優位になりやすくなります。心拍や血圧も安定し、ストレスを感じにくくなります。
さらに、姿勢が整うことで血流が改善し、筋肉のこりや頭痛、疲労感の軽減が期待できます。睡眠の質が向上し、朝スッキリ目覚められるようになる方も多いです。当院の患者さまからも「疲れにくくなった」「気分が前向きになった」といった声を多くいただきます。
日常の中で少し意識するだけでも、自律神経の乱れは整いやすくなります。デスクワークの合間に背筋を伸ばして深呼吸する、スマートフォンを見るときに画面を目の高さにする、椅子に深く腰をかけるなど、簡単な工夫が効果的です。
また、肩甲骨を寄せるストレッチや胸を開く体操は、浅い呼吸を改善し、副交感神経のスイッチを入れる助けになります。継続することで、姿勢の改善とともにリラックスしやすい体を作ることができます。
姿勢の乱れは体だけでなく心にも影響を及ぼします。交感神経が過剰に働くことで体が緊張し続け、イライラや不安、気分の落ち込みを引き起こすことがあります。逆に、姿勢を整えて深呼吸を意識することで、副交感神経が優位になり、気持ちが安定しやすくなります。
姿勢の崩れは代謝の低下にもつながります。筋肉バランスが崩れることで動きが悪くなり、疲れやすく太りやすい体質になることも。健康づくりの第一歩として、自分の姿勢を見直すことがとても大切です。
「なんとなく疲れが取れない」「最近、呼吸が浅い気がする」と感じるときは、まずは姿勢を確認してみましょう。日常の小さな意識の積み重ねが、体調の安定につながります。当院でも、姿勢分析や生活習慣のアドバイスを通じて、一人ひとりに合わせたケアを行っています。
姿勢と自律神経の関係を理解することで、毎日をより快適に過ごせるようになります。体と心の両方にやさしいケアを心がけ、バランスの取れた日々を送りましょう。