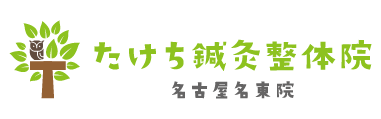
 院長:武智
院長:武智お気軽にご相談ください!
突発性難聴は原因不明で急に起こる聴力低下の症状で、早期治療が重要です。治療の中心となるのは「薬物療法」です。
ただ薬にも様々な種類があります。それぞれどのような作用があるかご存知でしょうか。
この記事では、突発性難聴の治療に使われる薬の種類、効果、使用方法について詳しく解説します。治療を検討されている方や、すでに治療を受けている方の参考になる情報をお届けします。
突発性難聴とは、内耳(聴覚器官)に何らかの原因で障害が生じ、その結果、突発性難聴という症状が出現します。
突発性難聴の感じ方は人それぞれ異なりますが
原因としては、内耳の血流障害、ウイルス感染、自己免疫疾患、聴神経の障害、ストレスなどが考えられていますが、明確なメカニズムは解明されていません。
突発性難聴が起きる原因が内耳の問題(血流障害・ウイルス感染・自己免疫疾患など)、神経系の問題(聴神経の障害・ストレスなど)であれば、
一般的には
などですが、その中で最も一般的に選ばれるものは「薬」です。
突発性難聴の治療は、発症から早ければ早いほど効果的です。特に発症から48時間以内、遅くとも1〜2週間以内に治療を開始することが回復率向上に重要です。発症から2週間を過ぎると、治療効果が著しく低下することが知られています。
突発性難聴に対する薬には様々な種類があります。


プレドニン錠(プレドニゾロン)、メドロール(メチルプレドニゾロン)、デキサメタゾン
突発性難聴の原因の一つとして、耳の奥(内耳)で炎症が起きている可能性が考えられています。ステロイド薬は、この炎症を強力に抑える働きがあるため、突発性難聴の治療で最初に使用されることが多く、いわば『主役』となる薬です。
炎症や腫れを鎮めることで、聴力の回復を目指します。飲み始めは効果をしっかり出すために多めの量で開始し、数日かけて徐々に量を減らしていくのが一般的です。これは、急に服用をやめると体のバランスが崩れたり、副作用が出やすくなったりするのを防ぐためです。
短期間の使用では重大な副作用が生じることはほとんどないと言われています。
アデコスホーワ腸溶剤(ATP)、カルナクリン錠、プロスタグランジン製剤、カルシウム拮抗薬など
耳の奥(内耳)には、音を感じ取るための大切な細胞がたくさんあります。これらの細胞が正常に働くためには、血液によって十分な酸素や栄養が届けられる必要があります。
突発性難聴の原因として、この内耳の血流が悪くなっている可能性も指摘されています。血流改善薬は、内耳への血の巡りを良くすることで、細胞の働きを助け、聴力の回復をサポートする目的で使われます。
メチコバール錠(ビタミンB12剤)など
※ビタミンB12は末梢神経を正常に保つためのビタミンで、難聴や耳鳴り、頭痛などに効果
これらの薬剤は症状に応じて、個別の症例や医師の判断で補助的に用いられることがあります。
※ただし抗ウイルス薬はウイルス感染が疑われる場合に限られ、標準治療の中心ではありません。
大前提として、突発性難聴を引き起こした問題が、内耳の問題(血流障害・ウイルス感染など)、神経系の問題(聴神経の障害・ストレスなど)、それ以外なのか知っておくことです。
そのうえで例えば、ウイルス感染によって炎症が起き突発性難聴が出現しています。その炎症を早く引かせる目的としてステロイド薬を服用します。
ステロイドなどの薬物療法は発症から2週間以内の急性期に最も効果が高く、それ以降は効果が限定的です。治療期間を過ぎてからの漫然とした薬物投与は推奨されていません。
「聴力低下」というのは体に問題があることを知らせる警報サインです。薬物療法は炎症や血流障害の改善を目的とした治療です。
突発性難聴の治療は、発症からできるだけ早く(48時間以内、遅くとも1~2週間以内)開始することが回復率向上に重要です。標準治療は、ステロイド薬(プレドニン等)を中心とした薬物療法で、ビタミンB12や血流改善薬も併用されます。
ステロイドは最初に多めに投与し、徐々に減量して1~2週間で終了します。副作用として感染症や胃潰瘍、血糖値上昇などがあるため、持病がある場合は医師と相談が必要です。治療開始が早いほど予後が良く、完全回復は約30~40%、部分的な改善が約30%、改善しない例も約30%です。
治療後も耳鳴りやめまいなどの後遺症が残る場合があります。内服や点滴で効果不十分な場合は、高気圧酸素療法や鼓室内ステロイド注入などの追加治療が行われることもあります
※必ず医療機関を初めに受診してください。